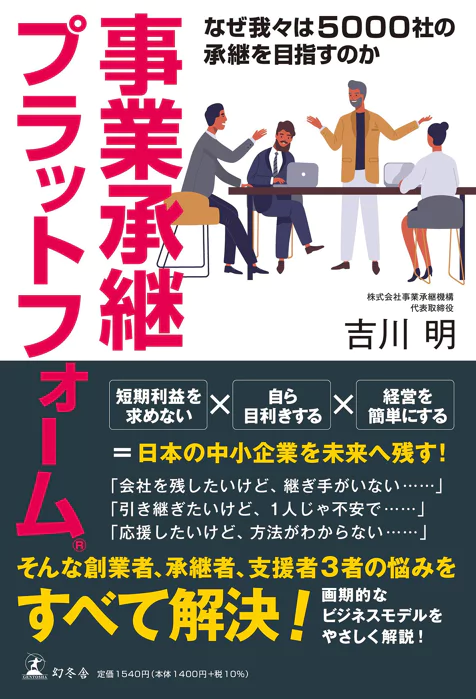先日、当機構設立時にお世話になったさわかみグループの澤上篤人会長から、大変興味深い話を聞いた。本物の長期投資とは? という題で、当機構のセミナーで講話頂いた時の話だ。それは、こんな話だった。
「本物の長期投資とは、1000年の目線で投資を行うことだ。想像できないかもしれないが、皆さんに分かるように実例を1つ紹介しよう。たとえば、14世紀頃のイタリアで権勢をふるったメディチ家は、銀行業で大成功して財を成した。教皇や王妃を一族から出すまでにもなったが、やがてその莫大な財産を、イタリアのフィレンツェを中心に文化・芸術のために長期投資した。具体的には、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロなどの才ある芸術家を見出し、大々的に支援し、これらの芸術家が作品を生み出すのを助けた。さらに、その作品を興行化するための博物館やオペラハウスなどにも巨額の投資を行った。その投資があまりにも多額であったことも家が傾いた一因と言われているが、それほど徹底的に文化・芸術に長期投資を行った。
それから6世紀を経た21世紀の今、そのリターンはもはや数字では図り切れないほどのものになっている。たとえばフィレンツェには、住民37万人に対し、年間1000万人以上の観光客が訪れ、毎年継続的に500億ドル超の観光収入をもたらしている。その観光収入をもたらしたのは、元を辿れば、メディチ家が6世紀前に長期投資を行ってフィレンツェに文化と芸術の種を蒔き、育てたからだ。また、定性的にも、フィレンツェは世界の芸術の都として確固たる地位を築き、人類の遺産と呼べるクラスの作品や、次世代の才能ある若者を続々と引き寄せている。古きを維持しながら、未来に向けた新たな文化や芸術を継続的に創出している。これが、600年超にわたる長期投資の実例であり、本物の長期投資だ。」
・・・さて、みなさんはこの話を読んで、どう感じただろう?「投資」を単なる「利殖」と考えてきた方には、天地がひっくりかえる程のインパクトがあったのではなかろうか?
正直、私自身、ハンマーで頭をガツンと打たれ、目から火花が飛び出るくらいのショックを受けた。本物の長期投資とは、JSKが目指している雇用・経済・安全の維持だけではなく、文化や芸術、さらに人の創造性や生き甲斐まで含めた、おそらくこの世のほぼすべてのものを支える土台(プラットフォーム)だというのだ。そして、6世紀も前から実例があり、現在も、そして未来に渡っても確実に必要なものだということだ。
本物の長期投資とは、いわゆる投資の教科書に載っている5年や10年を指すのではない。記録がデータ化されて残っており、インターネットで誰でも簡単に調べられるようになったわずか30年ばかりの時間軸でもない。国の政治家や官僚が考える、せいぜい自分の一生程度の50年や100年ぽっちの期間でもない。(この程度は少なくとも一部の人は考えていると願っているが・・・今日の、「自分が良ければ、自分の死後の子や孫の明日は知らん」と言わんばかりの政策主張が並ぶ選挙の様子を見ると、あやしいものだ)。
1000年先まで考えたときに、その投資が有意義と言えるのか。金銭的なリターンは当然に必要だが、社会的にも多面的なリターンを生む投資なのか。この点を、広く・深く・遠くまで想像をめぐらせ、不変の倫理観を持って判断し、他人が何と言おうと構わず断行するのが本物の長期投資なのだと、思い知らされた。私は、自分自身では、20年以上にわたり長期投資を研究し、永久保有の業態も開発し、精一杯実践してきたつもりだった。だが、ぜんぜんまだまだ足りないと痛感した。いまでもまだ、全然わかっていないと思い知らされた。
だが、これは良い気づきだ。逆に言えば、まだまだ私にもJSKにも、学び、改善すべき余地がたくさん残されているということだからだ。本物の長期投資を学び、実践していけば、よりよい投資を創り出すことができると気づけたのは、ありがたいことだ。
当機構がさわかみグループを卒業してもうすぐ3年になるが、いまも変わらずさわかみ会長は当機構を応援してくれている。卒業した後もかわりなく、「JSKの事業は世の中のために必要だ。ガンバレ!」と、いつも背中を押し、エールを送ってくれる。多忙にもかかわらず、当機構のセミナー講師も年数回は手弁当で行ってくれている。70代後半の会長が元気に熱く話をしているのを聞くといつも、こういう元気なプラチナシニアが増えれば、日本の未来はずっと明るくなる、と感じずにはいられない。そのシニア活躍の場を日本につくるのも、当機構の重要な役割だと思っている。
さて、では次に、永久保有のメリットに移ろうと思うが、その前にまず①永久保有とは何か、②どうすれば論理的に可能なのか? をご説明しよう。というのも、「永久保有」の話を皆さんにしても、多くの方が狐につままれたような顔をして、「本当に出来るの?」「そんなこと出来るわけない」という反応が、いまでも圧倒的に多いからだ。まるで100年前の人類に「このスマホという小さい箱で、遠くの人の顔を見てリアルタイムで話せるんだよ」という話をした時のような反応が、まだまだ圧倒的に多いのだ。
なぜ否定から入るのか? それはおそらく、これまでの人生で考えたこともなかった方が大半だからだろう。考えたことがないから、何のことかまったくわからない。まったくわからないものは怖いし、怪しいと判断し、否定するのは、生物学上当然の反応だ。だが、上記のスマホの例のように、理解出来なくとも、出来るものは出来る。そして、必要なものは必要なのだ。
だから、まず①永久保有とは何かを理解して頂き、次に、②どうすれば論理的に可能なのかを理解して頂き、それから③永久保有のメリット、をご説明しよう。
さて、では①永久保有とは何か。AI(Google Search)に聞くと下記の定義が表示される。
「永久保有とは、文字通り「永遠に保有すること」を意味します。投資の世界では、株式や不動産などを長期にわたって売却せずに、保有し続けることを指します。特に、株式においては、配当金や株主優待などを目的として、長期的に保有する戦略を指すことが多いです。」
上記の定義を因数分解すると、3つのキーワードが出てくる。つまり「永遠に」「売却せずに」「保有し続ける」の3つだ。ということは、この3つを成立させれば、永久保有は可能になるということだ。これを覚えて頂いて、次の説明に移ろう。
次は、②どうすれば論理的に可能なのか、だ。その答えは上記①で確認した3つのキーワードを満たすことだ。1つ1つ順番に見ていこう。
まず「永遠に」だが、これは時間軸を表している。つまり、長期投資の目線が1000年だとしても、それを遥かに超えて、1万年経とうが10万年経とうが、保有し続けるということだ。永遠の定義については、それほど疑義の無いところだろう。
2つ目の「売却せずに」というのは、意思に基づいて行為をしないことを意味している。つまり、「売る」という意思決定と行為をしないというコミットメントだ。ここは人の意思と行動なので、疑義を持つ人が多少は出てくるところだ。この疑義を乗り越えるには、長年の実績に基づく「信頼」しかない。「百聞は一見に如かず」という古い諺の通り、ヒトは言葉よりも行動を信じる生き物で、しかも信頼獲得には長い時間が必須だからだ。だから、当機構は早期に事業承継未来ファンドの運用を始め、1号ファンドはすでに運用開始から約4年が経過しようとしている。あと数年経てば、「売らずに事業承継を完了させ、かつファンドも償還した」という実績が出せる見込みなので、その時が当機構が実績を持って世の「信頼」を勝ち得て、大きく飛躍する時になるだろう。それまでも、もちろんセミナー等で出来ることはするが、実績がなければ信頼を勝ちうるのは困難だし、信頼の獲得には5~10年かかることは設立時から計画に織り込んであることなので、いまは無理をする時期ではないと考えている。やるべきことをきちんとやり、実績を示せば、信頼は後からついてくるものであり、あせって動いても天の時が来るまでは決して得られないものだからだ。
3つ目の「保有し続ける」というのが、おそらく多くのヒトが直感的に一番引っかかるところだろう。これは、意思に基づく行為と、意思に基づかない行為の両方を含むからだ。意思に基づく行為を信じるか否かは②と同じ信頼の問題なので、ここでは繰り返さない。だが、意思に基づかない行為とは何だろうか?たとえば、火事によって紙の株券を紛失することは、意思に基づかないが「保有し続けられなくなる」という一例だ。盗難や紛失等も同様だ。あるいは、会社の業績が傾き、倒産したらどうなるのか?という事態もここに含まれる。会社が倒産しても株券の保有は出来るが、銀行に担保として取り上げられたら、その時は法によって「保有し続ける」ことが出来なくなることもある。
また、会社の業績が好調であったとしても、「保有し続ける」ことが出来なくなる場合がある。たとえば、自然人が株を所有している限り、その自然人が寿命を迎えると「相続税」がかかる。会社の業績が好調であればあるほど会社の価値は高まるため、相続税も莫大な金額になる。ただ、未上場株は流動性が低いし、「売る」という行動は②や③に反するので、選択肢としては取れない。だから、相続税対策は十分にしておく必要がある。
ちなみに当機構では、当機構を設立する遥か前から、創業者の私がいつ死んだとしても、この①②③を守り切れるするにはどう設計しておくべきかを徹底的に考え、対策を施してある。詳細は省くが、弁護士や税理士等の専門家を複数交えて用意周到に考え、それをプラットフォームとしてビルトインした上で、当機構は設立され、運営されている。当機構は、①、②、③の条件を満たすには何が必要かを理解し、それを近い将来に満たすための体制も十分に整えているからこそ、「永久保有する」ことを方針としているのだ。
少しはご理解頂けただろうか? この①、②、③の条件を満たすのは、決して簡単なことではない。私自身も、その条件を満たす仕組みづくりのために、各界の専門家を交えて20年以上の時間をかけて研究開発してきた。法律や税制等の社会制度が複雑に絡む問題であるため、一般の方にわかりやすく説明するというのは不可能に近いとも思う。(たとえば、ご自身の相続税のことを考えてみてほしい。多くの方は、それだけでも理解は大変だろうが、私の場合はその数百倍の複雑さだと思ってもらえれば近いとは思う。)また、現在はようやく完成形が見えてその姿に近づいてきているが、それでも法律や税制、社会制度等が変わるとやはり影響を受けるために、毎年定期的な確認や修正は必要だ。
では、当機構はそこまで苦労してなぜ永久保有にこだわるのか? それは、永久保有には、それだけのメリットがあるからだ。ここで、再度AI(Google Search)に「永久保有のメリット」を聞いてみよう。下記の回答が示された。
永久保有のメリット
・複利効果の活用:
長期保有することで、得た利益を再投資し、雪だるま式に資産を増やすことができます。これは、投資期間が長ければ長いほど効果を発揮します.
・値動きによる精神的な負担の軽減:
短期的な値動きに一喜一憂することなく、長期的な視点で投資を継続できます。特に、株式市場全体の成長を信じる長期投資家にとっては、大きなメリットです.
・売買コストの抑制:
短期売買を繰り返すと、その都度手数料がかかりますが、長期保有であれば、売買回数を減らすことでコストを抑えられます.
・株主優待の長期的な享受:
一部の企業では、長期保有者に対して株主優待を優遇する制度を設けています。これにより、長期保有者はより多くの利益を得ることができます.
・安定的な資産形成:
短期的な利益を追求するのではなく、長期的な視点で資産を増やしていくことができます。これは、老後の資金形成や、将来の大きな買い物に向けての準備に役立ちます.
・配当金・株主優待の継続的な受給:
長期保有することで、定期的な配当金や株主優待を継続的に受け取ることができます。これは、安定した収入源を確保することにつながります.
・その他:
時間分散効果:長期保有は、時間分散効果も期待できます。
リスク分散:複数の銘柄に分散投資することで、リスクを分散できます。
・・・AIもまだまだだ。せっかく冒頭でさわかみ会長による「本物の長期投資とは?」といういい話をしたのに、この回答では単純な「利殖」の話だけではないか。。。。
まあ、本当に必要な情報はまだまだネットには載っていないことも多いし、AIもまだまだその程度のものなのだろう。だからこそ皆さんの時間を割いて、このような人手によって作成されたブログを読んで頂けてもいるので、AIが答えられなかった利殖以外の重要な点を3つ挙げよう。
第一に、「創業者と同じ長期視点で経営を出来る事」だ。多くの創業者は、株を売って現金にすることを目的に起業したり、経営をしてはいない。(最近は、ごく一部のITベンチャー等の経営者にはそういう方もいるようだが、当機構の対象外なのでここでは省く)。少なくとも当機構が引き受けている会社の創業者は、「国の役に立つ」「社会の役に立つ」「地域の役に立つ」「顧客・取引先の役に立つ」「雇用を守る」といった社会善を目的に会社を創業し、経営してきた方だ。そして、それを5年や10年という短期ではなく、多くの方は自分の生涯をかけて、実に30年から50年の長期視点で実行してきた方だ。それは、サラリーマン経営者の平均である2期4年とも、ファンドの平均投資期間である3~5年とも大きく異なる。視点の長さが、大きく違うのだ。
視点の長さが異なると何が変わるか? 判断が変わるのだ。たとえば、自分の任期の4年だけ利益を上げるなら、10年後の利益になる種の研究開発や設備投資、人材育成等の優先順位はどうしても低くなる。未来の種を蒔くよりも、今の刈り取りに全力を挙げる方が、利益は上がり、株価も上がり、経営者としても評価されるからだ。
だが、30年利益を上げる必要があるなら真逆で、研究開発や設備投資、人材育成等の優先順位が高くなる。このような長期の投資をしておかないと、企業の足腰が弱くなるからだ。もちろん中小企業の経営においても短期的な利益は必要だが、長期的な視点を併せ持つかどうかで、その判断は真逆なくらい変わってくる。このように、創業者と同じ長期視点で経営を出来ることは、永久保有の最大のメリットだ。
第二に、「その長期視点を、永久に継続出来る事」だ。経営者が自然人である以上、いずれ引退する時が来る。その時に、同じ長期視点を維持できるかどうかは、新旧経営者間の引継ぎ以上に、オーナーである株主が同じ長期視点を維持できるかにかかってくる。現代資本主義の仕組上、経営者は株主によって選ばれ、評価されるからだ。
その株主がファンドのように3~5年ごとに変わると、当然に経営者の選択方針も変わるため、経営方針がぶれやすくなる。固い地盤の上に立つ経営者と、水面に浮かぶ不安定な板の上に立つ経営者とが勝負をしたら、どちらが有利かは自明だろう。1度や2度ならたまたま後者が勝つこともあろうが、100回やれば90回は前者が勝つだろう。株主が永久に安定するということは、それだけで会社の経営上圧倒的に有利な環境を持てるというメリットがあるのだ。
最後に、「長期視点でガバナンスが出来る」ということだ。「君、君たらざれば、臣、臣たらず」という故事がある。株主は、現代資本主義において圧倒的な権限を持つ君だ。だからこそ、その権限は長期的かつ正当に行使する義務があると私は思っている(noblesse obligeに近い)。
その権限行使は、利益のためにする必要はあるが、利益のためだけではいけない。経営者に甘すぎても、厳しすぎてもいけない。従業員や取引先に対しても同様に、甘すぎても、厳しすぎてもいけない。万人が納得する判断はないが、独善に陥った判断ではいけない。自我を出し過ぎてもいけないが、自我を抑えすぎたら長続きしない。短期は重要だが、長期を無視してはいけない。日本のためになる判断は必要だが、世界のためという視点も無視してはいけない。そして何より、現世代の人たちのためはもちろんだが、遠い将来の子孫のためにもなる判断をする必要がある。
そのような長期視点でのガバナンスを行うのは、誰が行っても非常に困難だ。だが、永久に保有すると決めてしまえば、短期的な利益や目先の誘惑に魅かれることはなくなる。だから、その分は簡単になる。足場が不安定なところで振れないというのは不可能だが、軸が決まり足場が振れなくなれば、あとは実行あるのみになるから、その分簡単になるというわけだ。
今回は少し長くなったが、当機構の旗印である「永久保有」について、少しでも皆さんの理解を深めて頂く一助となれば幸いだ。最後に、MBA課程で最も印象的だったある教師の言葉を引用して、今回のブログを終えたいと思う。
「21世紀は、orではなくandの時代だ。利益or社会貢献、短期or長期などの単純な対立項ではなく、相矛盾することを同時に両立させることが出来る者が次の時代を切り開くのだ」