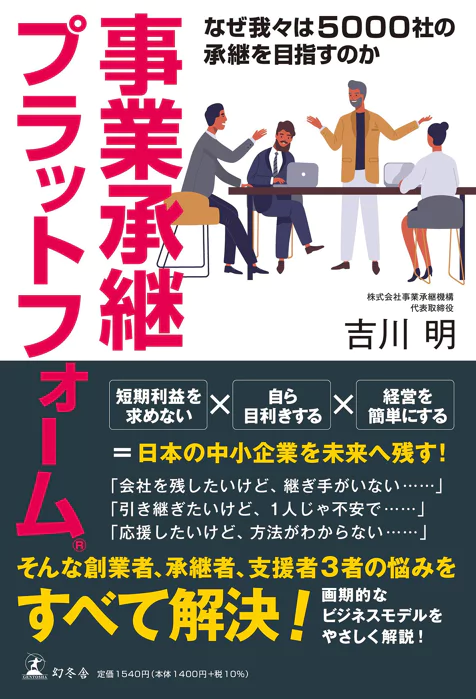もう4月、あっという間に半期が過ぎた。社長としてはうれしいことに、承継先からのニーズが日々増加傾向にあり、その対応でブログを書く暇もない充実した日々を送れている。だが、それでも弊社の事業を創業時から支えてくださっている皆様へのご報告を怠るわけにはいかないので、2~3か月に一度はブログを書き続けたいと思っている。(うちの広報の女性陣は、なかなかに厳しいのです・・・)
さて、この半期の間に、いままでになかった新しいパターンの事業承継が成立した。そこで今回は、そのうち2つの事例を取り上げて、その概要とポイントをご紹介していきたい。
1つ目は、「上場大企業の子会社の事業承継」が成立したという事例である。M&A業界においては「大企業子会社のカーブアウト」と呼ばれるパターンで、ファンドや大企業が買い手になるパターンが多い事例だ。だが本件では、大企業が弊社を「ベストオーナー」として選定され、当機構がお引き受けすることとなった。お相手が上場大企業であることもあり、詳細は下記の通り各社ホームページでリリースされているので、まずこちらをご一読頂ければと思う。
■ダイセルプレスリリース
https://www.daicel.com/news/2025/20250328_1091.html
■三井化学プレスリリース
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/release/2025/2025_0328/index.htm
■JSKプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000101784.html
本事例のように大企業の子会社をお引き受けするパターンは、正直、当機構としては1年程前まで想定もしていなかった。これまでに我々が取り組んできた事業承継は主に創業者個人が設立した中小企業であったし、大企業が設立した子会社を引き受けたいファンドや大企業は多数あり(いわゆるレッドオーシャンの市場)、業界でもファンドや大企業が引き受けるのがデフォルトのパターンになっているためだ。
本件のきっかけは、弊社への1本のあやしい(?)電話だった。
電話主:「あのー、△△(コンサルティング会社)の〇〇と申します。実は、弊社のクライアントが子会社の譲渡を検討しているのですが、御社がベストオーナー候補として選定されておりまして、ひいては一度ご面談の機会を・・・」
弊社社員:「はあ??? あ、はい。少々お待ちください」
(電話を保留にして、JSK社内にて)
「(承継担当の)〇〇さん、なんか変な電話がかかってきました! 代わってください!)
これが、きっかけだ。電話に出たのが管理部門の女性スタッフであったこともあり、最初は本当に怪しい電話なのではないかと思ったそうだ(昨今、怪しい電話が増えていることもあり、関係者の方々には笑ってお許し頂ければと思う)。正直、この時点では、私も何のことだか話がよくわからず、少し警戒もしたが、とりあえずコンサルタントの方にお会いして、お話を聞くことになった。
だが、当日現れたコンサルタントの方は、きちんとした会社の方だった。そして、その話を聞いて、目からうろこが落ちた気がした。ポイントとしては、永久保有を前提とした「雇用、企業風土、地域関係の長期的な維持」を求めているのは、中小企業の創業者だけではなく、大企業経営陣の場合もあるということだった。
JSKが開発した「事業承継プラットフォーム®」には、我々が想定していなかった使い道があり、それを大企業の方が自ら見つけて、ご連絡いただいたのだ。JSKが提供する「事業承継プラットフォーム®」のうち、特に先方にご評価いただいたのは、「永久保有(転売しない・統合しない・移転しない)」と「手厚い支援体制」であり、またその実績を積み上げてきていた事実であった。当機構がこれまで愚直に積み上げてきた実績が、新たなパターンを呼び込む礎となった、とも言えるだろう。
先方が上場大企業であり、しかもその上場大企業の中でも古豪の名門であるダイセルと三井化学という2社であったこともあり、本件の交渉や調整は、対個人創業者とは違う意味で大変だった。弊社自身もまだまだ中小企業なので、レベルの差は大きく、きっと両社の関係者の方々にもご苦労をおかけしたのだと思う。この場をお借りして、両社の関係者の方には改めて御礼申し上げたい。
だが、先方の「対象会社の今後のために、従業員の雇用維持・企業風土の尊重を最優先する。そのためには、JSKがベストオーナーだ」という意思決定は、1年以上の間、最初から最後まで揺らぐことはなかった。むしろ、交渉過程で壁にぶち当たるにつれ、より輝きを増し、北極星のようにブレない指針になっていったように思えた。
当方としても、その想いに何度も触れ、真摯に受け止めて真剣に対応することで、本件は2025年3月27日にクロージングを迎えた。失礼な言い方になってしまうかもしれないが、日本の名門企業を率いる経営陣の「矜持」を強く感じ、非常にうれしく、また頼もしく思った事例であった。
皆様もご存じの通り、昨今の資本市場は劣化してきており、「いまだけ、カネだけ、自分だけ」という、強欲資本主義が跋扈している。それに賛同する株主も、残念ながら増えている。先日はついに、世界一の大国である米国の大統領までもがそのような振る舞いを正当化して、巨額の関税を発表したばかりだ。
その中で、上場企業の経営陣として資本市場と堂々と折り合いを付けながらも、これまで会社を支えてきた子会社の従業員、その独自の企業風土を最重要視し、自社としては手放さざるを得ないものの子会社のために出来る限りのことはして送り出そうという、日本人ならではの美しい心を持ち、またそれを貫徹する実行力を合わせ持つ経営陣が、日本の大企業にはまだいるのだ。本件を通じてそのことを実感することが出来、純粋に、とても嬉しく思った。こういう方々が大企業を率いるのならば、たとえ目先で世界的に経済が混乱したとしても、日本の大企業はまだまだ大丈夫だろう。逆に、世界的に短期の拝金主義が横行する中で、日本ならではの長期的な美意識・価値観に基づく判断が輝きを増す時代が、すぐそこまできているのかもしれないとも思う。
当機構にとっても私自身にとっても、生涯忘れることがないであろう、「事業承継プラットフォーム®」の新しい大きな可能性に気付くことが出来た事例であった。
さて、もう1つは、銀行グループと組んで事業承継が成立した、という事例だ。こちらも銀行グループからプレスリリースがなされており、詳細は以下の通りである。
■りそなホールディングスプレスリリース(株式会社みなと銀行、りそなキャピタル株式会社、みなとキャピタル株式会社の連名)
https://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/hd_c/detail/20250331_3679.html
■JSKプレスリリース
https://jigyosyokei.co.jp/news/a20250331/
本件の特徴は、銀行グループが、ローンの提供のみならず、エクイティ部分も提供したという点だ。銀行系のキャピタル子会社が運用するファンドからエクイティを提供して頂くことで、JSKは資金をほぼ使うことなく、永久保有型の事業承継が成立した。
本件においても、成立のポイントになったのは、「永久保有」、「雇用や企業文化の長期的な維持」、そして「長期的な経営支援」の3点であった。この3点は、今後もずっとJSKのキーワードになるので、ぜひ皆様にもご認識頂ければと思う。
1点目の永久保有については、銀行法の改正以来、ファンドを設立した銀行は多数ある。りそなグループは、そのトップランナーに位置する銀行であり、投資実績も豊富だ。だが、銀行系とはいえファンドには変わりないので、その仕組上、そもそも永久保有は不可能だ。
そのため、永久保有のニーズを希望される銀行のお取引先企業には、永久保有を可能にするJSKの「事業承継プラットフォーム®」をソリューションとしてご提供頂くことが有効であると銀行にご判断頂けたことが、本件の起点であった。また、JSKの「事業承継プラットフォーム®」は、銀行ファンドと競合するというよりも、お客様のより広いニーズに応えるための銀行のソリューションの1つであり、お客様のために銀行としては持っておくべきソリューションであるとご判断頂けたことも重要だった(この点は、全国の他行にもご理解頂けたら、その地域の事業承継問題の解決を加速する大きなポイントになると思っている)。
2点目の「雇用や企業文化の長期的な維持」については、永久保有を前提にしているから無理なくコミット出来るというのが、「事業承継プラットフォーム®」の強みだ。ファンドでは数年での転売が前提であるところ、自社が売るのに雇用や企業文化の長期的な維持にもコミットするというのは矛盾した話になってしまう。だから、雇用や企業文化の長期的な維持をなによりも優先されるお客様のニーズに応えるには、銀行系ファンドよりも当機構の「事業承継プラットフォーム®」の方が適しているのだ。
さらに、3点目は、経営支援の人材の厚みと、実績の違いだ。銀行系のファンドは、銀行系であるために、当然に資金は潤沢にある。他方、銀行でも人材不足は課題であるところ、さらに融資とは異なる投資のノウハウが必要なファンド人材の不足や、承継後の中小企業の経営ノウハウ(特にハンズオン現場においての)に悩む銀行は、少なくない。
その解決策としてJSKの「事業承継プラットフォーム®」を代用し、銀行の人材不足とノウハウ不足をカバーしながら、お取引先の企業価値向上を自行が行う以上の体制でJSKが行うことに価値を見出していただくことで成立したのが本件だ。
JSKには、すでに国内のファンド運営会社としては最大級の、60名超の内部人材がいる。その8割は実業界で実績を上げてきたメンバーであり、また半数は社長もしくは役員といった経営実務の経験者であるなど、質的にも日本最高クラスのメンバーがそろっている。
さらに、JSKの独自リストには600名以上の登録人材がおり、たとえば本承継先企業に対しても、経営実績を豊富に有する社長を担当チームとともに推薦することで、承継後の経営体制をクロージング前から整備し、万全の体制で引継ぎを開始している。
JSKが提携先銀行の課題であるノウハウや人材面でのソリューションをご提供しながら、銀行には本業である融資や資本の提供に集中していただき、両社の強みを活かし、弱みを補完する共同ビジネスとして、地域の企業を地域内に永久に残していく取り組みだ。
このパターンは銀行系ファンドを持つ他の銀行でも可能なので、全国的に展開することができれば、中小企業の事業承継問題の解決が大きく進むと考えている。餅は餅屋であり、得意分野に集中することが生産性向上につながることは経済学の原則であることから、これもまた大きなポテンシャルを秘めた共同の事例だと思っている。
今回は新しいパターンを2つご紹介させて頂いた。その他にも、足元では候補先企業のニーズに応じて続々と新たなパターンが生れてきている。「事業承継プラットフォーム®」には、私も気づいていない大きな発展性があるのかもしれない。
上記2つの事例のプレスリリース以降、複数の会社から「うちでもこういうのが出来ないか?」というお問い合わせを頂いており、弊社スタッフ一同嬉しい悲鳴を上げているところである。
これらは、過去6期間、当機構メンバー一同が、日本のために、子や孫のためにと、真摯に活動してきた結果ともいえる。その結果を誇りに思う。また、今年の活動が6年後により大きな実を結び、子や孫のために日本の事業承継問題を全面的に解決することにつながるように、「夢は大空に、努力は足元に」を旨として、社員一丸となって今日も活動していこう。